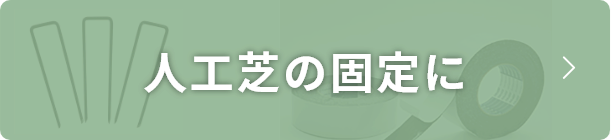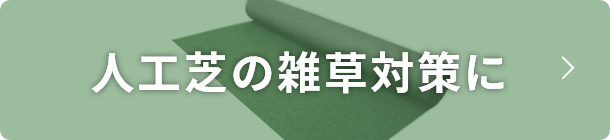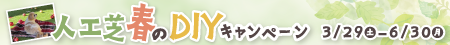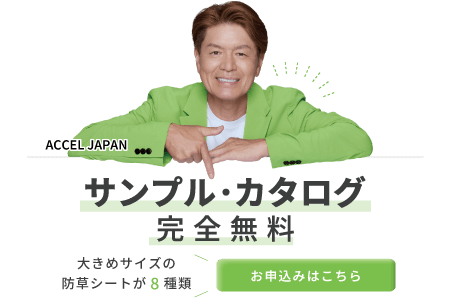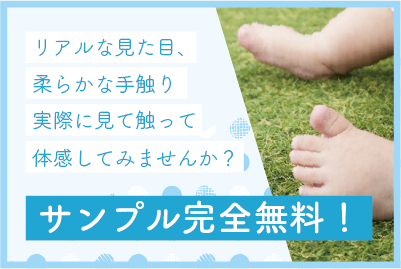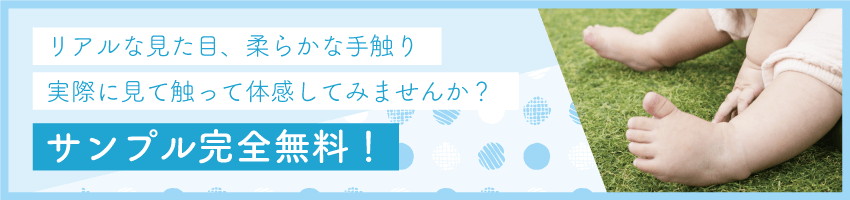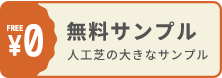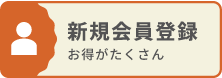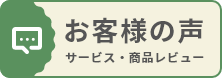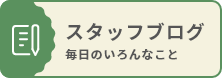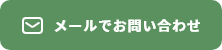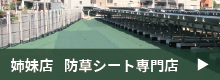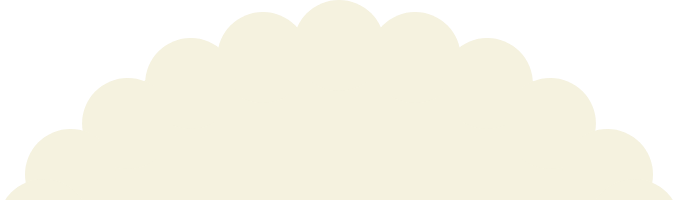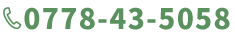庭の雑草対策完全ガイド!効果的な方法とアイテムを徹底解説
せっかくの庭が雑草の手入ればかり増えているとお悩みの方、多いのではないでしょうか。
伸び放題になっている雑草を放置すると、景観を損ねるだけでなく害虫や害獣の温床になることもあります。

庭の雑草対策に向けて
雑草が多く生える一番の原因は、植物が育ちやすい環境が整っているからです。
土壌の水分が豊富にあり、日当たりや通気性が良ければ、種や地下茎を持つ雑草は急激に繁殖します。
ここでは、なぜ庭で雑草が増えやすいのかを解説します。
雑草が増えてしまう理由
雑草が増える背景には、手入れ不足や土壌条件が影響しています。
とくに春から初夏にかけて降雨量が多くなると発芽・成長が急激に進み、あっという間に庭を覆ってしまうことがあります。
早めに適切な対策を取れば、雑草の成長を大きく抑えられます。
庭の雑草対策の比較
さまざまな対策法を見比べると、それぞれのメリット・デメリットがわかりやすくなります。
どの方法が自分の庭に適しているか、下表を参考にしてみてください。
主な対策方法の比較
| 対策方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 全面コンクリート | 雑草をほぼ防げる。耐久性が高い。 | 殺風景になりやすい。夏に熱がこもる。高コスト。 |
| 除草剤 | 短期的に雑草を除去できる。専用の雑草に特化した除草剤もあり、幅広く対応できる。 | 農薬のため取り扱い注意。定期的な散布が必要。 |
| 防草シート | 雑草をしっかり抑制できる。耐久性の高いシートを選べば長期間雑草を抑えることができる。 | 耐久性の低い安価な防草シートは劣化が早い。 |
| 砂利敷き | 施工が比較的容易でコストが抑えやすい。防草シートとの併用で高い防草効果が得られる。 | 砂利の隙間に入った落ち葉やゴミが掃除しにくい。 |
| ウッドチップ | 見た目がおしゃれ。防草シートとの併用で高い防草効果が得られる。 | 虫や経年劣化に弱い。 |
| 人工芝 | 初心者でもdiyで施工がしやすい。防草シートとの併用で高い防草効果が得られる。メンテナンスが楽。 | 初期費用が高い。 |
| 防草土(固まる土) | 初心者でもdiyで施工しやすい。整地により均一な表面になる。 | 強度が低く割れが生じる。水はけによっては苔が発生する。 |
| 草むしり(手作業) | 確実に雑草を除去できる。低コスト。 | 重労働で熱中症リスクがある。広い面積には不向き。 |
| 塩・熱湯 | 手軽で身近な方法。 | 土壌や建物に影響が出る可能性がある。根を完全に枯らすことができない。 |
一度施工した後も定期的な点検とメンテナンスを続けることが、雑草を寄せつけない庭を維持するうえでとても重要です。
庭の雑草対策カレンダー
庭の雑草は季節ごとに生育スピードが異なります。
雑草対策を適切なタイミングで行うことで、労力を最小限に抑えることが可能です。
ここからは、年間を通してどのような作業が望ましいのか時期ごとに見ていきます。
春の雑草チェック

3月から4月にかけては、雑草がまだ小さい状態です。
地温が上がり始めるタイミングなので、この時期に目立ってきた雑草を早めに抜いておくと、後々の除草の苦労を抑えることが出来ます。
雑草が少ないうちに除草剤や防草シートで対策をしておくのがおすすめです。
初夏の急成長への対処

6月から7月は雨が続く分、雑草がぐんぐん伸びる時期です。
特にスギナなどの地下茎を張る雑草は、一度伸び始めると驚くほどのスピードで繁茂します。
週に一度のペースで庭を確認し、伸びてきた雑草をこまめに除去するのが理想的です。
梅雨の晴れ間に不要な雑草を取り除けば、被害を最小限に抑えられます。
真夏の作業の注意点

8月から9月にかけては暑さのピークを迎えます。
炎天下での草刈りや除草作業は熱中症リスクが高いため、朝や夕方の比較的涼しい時間帯に作業することを心がけましょう。
蚊や虫対策として、長袖や防虫スプレーも用意しておくと安心です。
体力的にも負担が大きい時期なので、無理のないペースで定期的な除草を行い、庭全体を健康的な状態に維持するよう努めましょう。
秋の除草と落ち葉対策

10月から11月は気温が下がり始めますが、雑草の中にはこの時期に種を飛散させるものがあります。
種が飛散してしまうと翌年の雑草発生が増えるため、秋の終わりにまとめて除去しておくと翌年が楽になります。
また、落ち葉がたくさん積もるタイミングでもあり、放置するとその下で雑草が育つことがあります。
こまめに掃除しながら雑草の発芽もしっかりチェックすると良いでしょう。
冬の雑草が落ち着く時期の対策

12月から2月の寒い時期は、雑草のほとんどが活動しません。
この時期に大がかりな除草剤の散布や地面の工事を行う必要はあまりありません。
ただし、防草シートの敷き直しや排水の調整など、次のシーズンに備えた下準備をするには適したタイミングです。
地面の凍結にも注意しつつ、できる範囲で庭のメンテナンスを行うのがおすすめです。
庭に生えがちな頑固な雑草の対策
このような雑草対策をしていても、あっという間に復活してしまう厄介な種類を見かけることがあります。
特に地下茎が強いものや種が飛散しやすいものは、丁寧に対処する必要があります。
ここでは、代表的な5種類の頑固な雑草と、その対処法を解説します。
ドクダミの対処法

ドクダミは地下茎が太く、一度根付くと手ごわい存在です。
茎を少し切っただけでは、地中の根からあっという間に新芽を出します。
新芽が出る前に防草シートを敷いて日光を遮断すれば、行く行くは地下茎まで駆除することができます。
重点的に対処したい場合は、根こそぎ掘り起こすか、ドクダミに効果の高い選択性除草剤を使うと効果的です。
土の中に残らないように気を配りながら根元を撤去しましょう。
スギナの対処法

スギナはツクシで知られるトクサ科の植物で、地中深くまで根をはるのが特徴です。
薄手の防草シートを貫通して伸びてくる例もあり、頑丈さがうかがえます。
本格的に駆除するには、地上部を刈り取った後に防草シートを敷きます。
また、スギナに効果の高い選択性除草剤でピンポイントに除草するのも効果的です。
ヤブガラシの対処法

ヤブガラシはツルが周囲の木やフェンスに絡みつき、気づかないうちに広範囲を覆い尽くす雑草です。
地下茎も強靭で、切れた根から再生するため油断は禁物です。
対策としては、ツル自体を根元付近から刈り取って光合成をさせずに弱らせる方法が挙げられます。
除草剤を使う場合は、葉から吸収させるタイプをじっくり浸透させると効果的です。
コニシキソウの対処法

地を這うように生育するコニシキソウは、ちぎれやすい茎が特徴的です。
抜こうとすると茎が切れて根が残り、そこからまた広がってしまう厄介さがあります。
抜く際にはゆっくり根本から引き抜き、残さないようにすることが肝心です。
表面の土を軽くほぐし、根がスムーズに抜ける状態で対処すると再発を抑えられます。
カタバミの対処法

カタバミはハート形の葉がかわいらしく見える反面、種が弾け飛ぶことで周辺一帯に急速に拡散します。
種が熟する前に引き抜くのが最も手軽な予防策となります。
根が深い場合は、こまめに除去を繰り返して増殖を防ぐ手順が必要です。
葉にエネルギーを回さないように定期的に除草し、土中の種子も発芽時に早めに取り除くと効果が高いです。
まとめ
庭の雑草対策は、種類と季節に合わせた年間管理が重要です。
時期や気候に合わせた対策の準備をしておき、早めの除草と定期的な手入れを怠らなければ、雑草の少ない快適な庭を維持できます。
ここで紹介したような頑固な雑草を見つけたら、根気強く丁寧な対処を施しましょう。