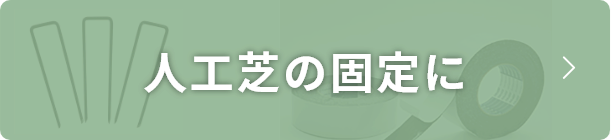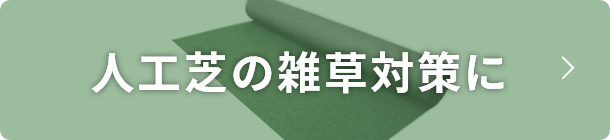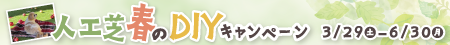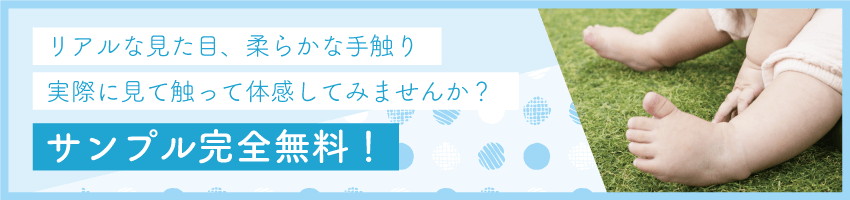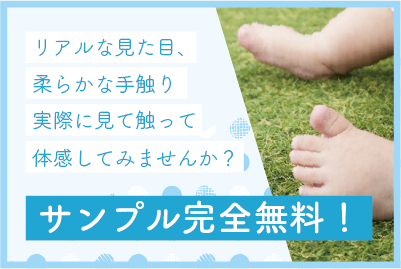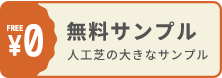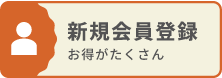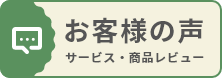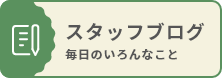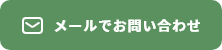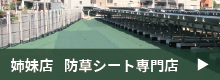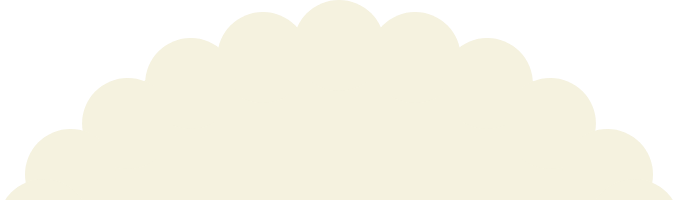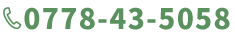人工芝の静電気トラブルを未然に防ぐ方法をご紹介
人工芝はお庭やベランダの景観維持に便利な反面、冬場などの乾燥した時期に静電気が発生しやすい点に悩む方が多いようです。
そこで、この記事では人工芝の静電気トラブルを未然に防ぐためのヒントを紹介します。
素材や環境への理解を深め、スムーズに対策を始められるように情報をまとめました。

人工芝の静電気が起こりやすい理由
人工芝を使用する上で静電気が起こりやすい背景にはいくつかの要因があります。
ここでは代表的なポイントを簡単に確認し、その後に具体的な対策を説明します。
プラスチックの帯電性による影響

人工芝にはナイロンやポリプロピレンなどのプラスチック素材が使われています。
プラスチックは電気を通しにくい絶縁体で、摩擦によって電荷が蓄積しやすい性質を持ちます。 たとえば下敷きを髪の毛に擦り付けると髪が逆立つ現象も、この帯電特性によるものです。人工芝も同様で、冬場の乾燥状態や人の動きによって静電気が生じやすくなります。
人工芝の静電気を完全にゼロにするのは難しいですが、素材をある程度理解しておくと参考になります。静電気防止加工がなされた人工芝を選ぶ際にも、どの素材がベースなのか意識してみると良いでしょう。
摩擦による要因

人が歩いたり触れたりする摩擦は帯電の大きな要因になります。
人工芝の上を裸足で歩くと、足裏との接触面で電気が帯電しやすくなります。
特に室内などでフローリング上に人工芝を直敷きした場合、床に電気が逃げにくく静電気が残りやすいです。
乾燥による要因
冬場は空気中の水分が少なくなるため、放電が起こりにくい環境です。
つまり空気が乾くと電荷が溜まりやすいので、日常的な動作の中でパチッとくる現象が起こりがちです。
特に、人工芝を敷く機会の多いテラスやベランダでは、日当たりの良さが乾燥を進める要因となる場合があります。
日差しが強い時間帯には人工芝の温度も上昇しやすいため、より摩擦が増して帯電が強まることもあるのです。
静電気が発生しやすい条件
対策を考える上では、人工芝を敷く環境や季節も重要です。
ここでは静電気が特に起こりやすい時期と、場所ごとの注意点について触れます。
冬場や空気の乾燥が続くシーズン
冬場は湿度が低下しやすいため、あらゆる素材で静電気が起こりやすくなります。 人工芝も例外ではなく、人の移動が増えるほど帯電しやすいと考えておくと良いでしょう。
暖房で室内が暖まりすぎると、さらに乾燥が進むことがあります。また、冬場でも晴天が続く地域では屋外も非常に乾燥しがちです。 乾燥が続きそうな日は、こまめに水を撒いたり静電気除去グッズを活用したりすることが重要となります。
日照時間の短い地域や積雪のある地域では、雪解け後の急な乾燥にも注意が必要です。
ベランダや室内

コンクリートやフローリングの上に人工芝を直敷きすると、地面(床)へのアースがうまく機能しません。
結果として、体に帯電した電気が抜けにくくなる傾向があります。
室内の場合は特に、空調の効いた環境で静電気が蓄積しやすいため、意識して除電アイテムを取り入れることがおすすめです。ベランダに敷く場合も、下に排水用の溝があると電気が逃げにくいケースがあります。
いずれにしても、床下との間にわずかな隙間を作る工夫や、導電性のあるシートなどを活用することで静電気の軽減を狙えます。
マンションやアパート

マンションやアパートなどの集合住宅では、隣の部屋との壁や床を通じての放電がしにくい場合もあります。
階下への騒音対策として人工芝を使う際には、付随する静電気への配慮もセットで行うとより安心です。
人工芝に発生する静電気の対策方法
最後に、実際に使える帯電対策を見ていきます。
それぞれの方法に特徴があるので、状況に応じた選択が大切です。
静電気対策済みの人工芝を活用

より静電気を抑えたい方には、帯電防止機能が施された人工芝がおすすめです。
帯電防止剤が組み込まれたタイプの人工芝は、価格は高めですが、摩擦による電荷の蓄積を一定程度抑えられるため、強い静電気を感じるのが苦手な方や、小さなお子さまがいる家庭には魅力的な商品です。
なお、帯電防止技術にはさまざまな種類があり、導電性の繊維(導電性パイル)を織り交ぜてある製品も存在します。
こうした人工芝は、中に導電性パイルを組み込むことで蓄積した電気を地面へ逃がし、静電気の発生を効果的に抑制しています。
施工後の見た目や肌触りに大きな影響はないため、一般の人工芝と同様に楽しむことが可能です。
当店のふわふわターフは、静電気を防ぐ性質をもたせた導電性パイルを織り込んだ人工芝ですので安心してご利用いただくことができます。
静電気除去シートの利用

引用元:Amazon
出入り口付近に静電気除去シートを貼っておくと、屋内外を行き来するときに帯電が物理的にリセットされやすくなります。 床に敷くタイプもあれば、手で触れて除電するタイプもあります。
玄関先などの通り道にシートを設置しておくと、無意識のうちに余分な電気を逃がすことが可能です。小さなマット状の製品も市販されており、そこを踏むだけでパチッとくる不快感を軽減できます。
ただし、シートの効果は永久的ではないため、定期的に交換するか、摩耗しにくい耐久性のある製品を選ぶと長持ちしやすいです。
静電気防止スプレーを使う

引用元:Amazon
もっと手軽に対策を行いたい場合、静電気防止スプレーが活躍します。 必要な時にシュッと吹きかけることが出来るので、コスト面でも導入しやすい方法です。
人工芝全体に吹きかけるほか、足元に軽くスプレーしても帯電を軽減しやすくなります。ペット用のスプレーもあるため、動物と遊ぶ機会の多い方にもおすすめです。
ただし人工芝の場合は、表面にしっかりとスプレー成分が接触しないと効果が薄れる可能性があります。
また、室内への出入りが多い場所では、玄関周りだけ重点的にスプレーを使う方法やポイントを絞った使用も有効です。
服装で帯電を軽減する
ウールやナイロンの衣類は擦れることで電荷を帯びやすい特徴があります。
静電気を抑えたい日は、木綿素材の服が安心です。
家の中で靴下を脱いで過ごす場合など、肌と衣類が直接こすれ合うシーンが多いほど帯電のリスクは高まります。
また、フリース生地のような起毛したアイテムも注意が必要になります。
空気を含みやすく温かい反面、乾いた環境での帯電が起こりやすいため、特に冬場は注意が必要です。
靴下などのインナーアイテムを見直すだけでも、体に帯電する電気量を抑えられるケースがあります。
たとえば綿混素材のソックスや下着を選ぶことで、微妙な摩擦が少なくなり、結果的に静電気を和らげます。
水を撒いて湿度を保つ
空気が乾燥していると人工芝に静電気が発生しやすくなるため、水分を適度に与える手段です。
霧吹きなどで全体を軽く濡らしてあげるだけでも帯電しにくくなります。
ただし冬場や気温が低い季節では、水を撒くことで芝が冷たくなり、足元の不快感が増す場合もあるので注意しましょう。
屋外の場合は凍結リスクも考慮し、気温条件に合わせて実施することが大切です。
水撒きが面倒に感じる場合は、空気の乾燥度合いを抑える加湿器を使うのもおすすめです。
特に室内に人工芝を敷いているなら、加湿器との併用で冬にも快適さをキープしやすくなります。
なお、人工芝の下地が砂や砕石の場合は、水を撒いても地面に吸収されやすく、思ったほど湿度が保てないこともあります。
定期的に観察しつつ、水やりのタイミングを検討すると良いかもしれません。
まとめ
ここまで見てきたように、静電気の発生は素材の特性や湿度の低下など、さまざまな要因が複雑に絡み合って起こります。
そのため、一つの方法だけで完全に防ぐのは難しく、複数の対策を組み合わせることが重要です。
特に、導電性のパイルを組み込んだ制電機能付き人工芝は蓄積した静電気を効率よく地面へ逃がし、静電気の発生を大幅に抑制できる有効な選択肢の一つです。これを庭やベランダに敷くことで静電気による不快感を軽減し、快適な環境を維持できます。
さらに、帯電防止スプレーや適切な湿度管理を併用することで、より効果的な対策が可能です。
生活空間に適した方法を試しながら、自分に最適な静電気対策を取り入れ、より快適な空間づくりを進めてみてください。